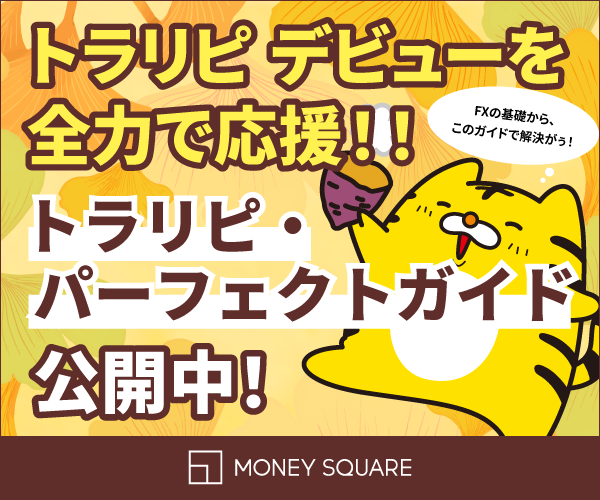≪2019.1.31作成≫twitter➡けだま@kedamafire
FX投資を行う人にとって2019年の初めは刺激と学びの多い1ヵ月となりました。
なんといってもフラッシュ・クラッシュ(瞬間暴落)です。
▼関連記事|フラッシュクラッシュの回避は不可能。だからこそ意識しておく必要があること。
数百万、一千万単位でロスカットとなった人はもとより、運よくケガをまぬがれた人にとってもFX投資をするうえで常に頭の片隅に置いておかなければならないリスク=投資金額が一瞬で消えてなくなるリスクをあらためて意識することとなったのではないでしょうか。
★★★
つい先日、中国の習近平国家主席が講演で行った発言に関するニュースから、年始のことを想起しました。
そのニュースとはこんな内容。
中国国営新華社通信が報じたところによると、習近平国家主席は今後の経済についてこう語ったとのこと。
ブラックスワンだけではなく、
灰色のサイも防がなければならない。
ブラックスワンとは、
めったに起きないが、発生すれば極めて大きな影響を及ぼす問題。を指します。黒い白鳥はめったに現れないことに由来。
ナシーム・ニコラス・タレブ著で、2007年に全米150万部超のベストセラーとなったタイトル『ブラックスワン』(副題:不確実性とリスクの本質)の内容から比喩的に使われています。
灰色のサイとは、
高い確率で起こるが発生すれば何もできず見ているしかないリスク。を言います。サイは灰色が普通で普段はおとなしい。だが暴走し始めると誰も手を付けられなくなることに由来。
米国の作家ミシェル・ワッカー著の『グレー・リノ(灰色のサイ)』で示された内容から引用されています。
★★★
中国における「灰色のサイ」とは、高成長の代償として積み上がった高い民間債務。
日本と中国の非金融部門の民間債務を対GDP比でみると、日本157.5%に対し、中国は205.5%。中国の数値は日本のバブル期の水準に近いものです。この水準の高さが中国経済崩壊論の論拠の一つとされています。
▼参考|ロイター通信|中国の多額負債を抱えるゾンビ企業問題
★★★
FX投資で言うところの『ブラックスワン』とは、まさにフラッシュ・クラッシュ(瞬間暴落)ですよね。
『灰色のサイ』は言うなれば普段の資金管理といったところでしょうか。(油断して低い証拠金維持率で運用していてのロスカットは、起こるべくして起こる)
★★★
この、FX投資における『ブラックスワン』と『灰色のサイ』を予防するための鉄則とすべきものを最近読んだ本から見つけたので紹介します。
その本とはこちら。

ウィリアム・ディルバート・ギャン著
ウィリアム・ディルバート・ギャンは、テクニカル分析の始祖と言われる米国人投資家。
1929年の世界大恐慌を的確に予測し、投資の生涯勝率は8割以上だったと言われる伝説の投資家です。
当たり前ですが投資をしていると難しさがわかりますよね。これはつまりキャッシュ・ポジションの的確な管理ということです。
資金の10分の1以上損失が出るような仕掛け方はしない。というルールを保っていれば、フラッシュ・クラッシュ(瞬間暴落)に巻き込まれても傷は浅い。
ブラックスワン=“めったに起きない” ( = フラッシュクラッシュ ) が、” 発生すれば極めて大きな影響 “( ロスカット )を及ぼす問題。
前者には対処できないため、後者のロスカットによる傷を最小限にするということが唯一有効な戦略ですよね。
投資において事前に正確に計算することができるのは『損失』だけです。
利益は全て仮定の計算となり、不確実。
ですので、FX投資であればストップロス(逆指値)を必ず設定することがリスクヘッジの鉄則です。
★★★
この2つの鉄則に従うことで、FX投資における『ブラックスワン』と『灰色のサイ』を克服できるはずです。
シンプルで当たり前のことが実はとても実行が難しいわけですが、フラッシュ・クラッシュ(瞬間暴落)はリーマンショックなど「〇〇ショック」に比べて発生確率は高いため、しっかり対処しておきましょう(^^♪
それではまた~
▼関連記事|投資のリスクとリターンは正比例する
▼FXよりも米国株投資がメインです
①楽天証券での米国高配当株投資
②ワンタップバイでの米国株投資
★★★
▼投資・経済関連コラム的記事
記事リンク:今日の1分脳内
▼資産運用関連のNews|Topic記事
記事リンク:News|Topic一覧
▼資産運用実績
記事リンク:運用実績
▼資産運用スタートマニュアル
記事リンク:スタートマニュアル
★★★
それではまた~
Twitter➡けだま@kedamafire
応援のクリックをお願いします♪
![]()
にほんブログ村
 使いやすさNo.1楽天証券
使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |
|---|---|
| コスト | |
| 情報量 |
 ドル転コスト№1SBI証券
ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |
|---|---|
| コスト | |
| 情報量 |
 米国株の情報量が豊富!マネックス証券
米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |
|---|---|
| コスト | |
| 情報の豊富さ |
ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、
メイン利用は楽天証券、
ETF積立はSBI証券、
情報収集はマネックス証券
と使い分けしています。