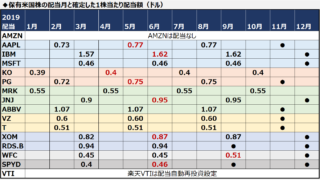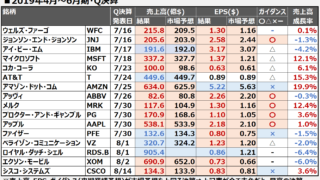こんにちは、けだま(@kedamafire)です。
ここのところ、ちらほらと『ゾンビ企業』なるワードを目にすることが多くなってきました。
特に個別株投資をしている方やこれから投資をはじめる方にとっては、知っておいて損はないワードです。
記事は大体2分程度で読める分量です。読み進めてみてくださいね。
- ゾンビ企業ってなに?
- ゾンビ企業が増えている。なぜ?
- ゾンビ企業への投資は避けたい!どこに注目すればよい?

ゾンビ企業ってなに?

結構昔から使われ始めた表現で、日本では1990年代前半のバブル崩壊後、長らく日本経済が停滞した「失われた10年」を専門家が語る際に登場したとも言われています。
日本経済新聞の記事を引用すると、
数年にわたって債務の利払いすらままならず経営が破綻状態にあるのに、銀行や政府などの支援によって存続しつづけているような企業を指す。
≪引用元:日本経済新聞-2019年2月9日≫
ひと言で言うと、
借金の利払いを利益で賄えておらず延命状態の企業
ってことですね。
国際決済銀行(BIS)でも『ゾンビ企業』について、
3年以上に渡ってインタレスト・カバレッジ・レシオ(利払い負担に対する利益の比率)が1未満にある企業
と定義付けされています。
この急速に膨らむ『債務』への注目は、特に中国のリスクとしても話題に上ることが多く、米中貿易摩擦が激化した2019年初めからこんな記事を目にされた方も多いのではないでしょうか。
≪出所:Business Insider Japan≫
ゾンビ企業が増えている。ってそれはなぜ?
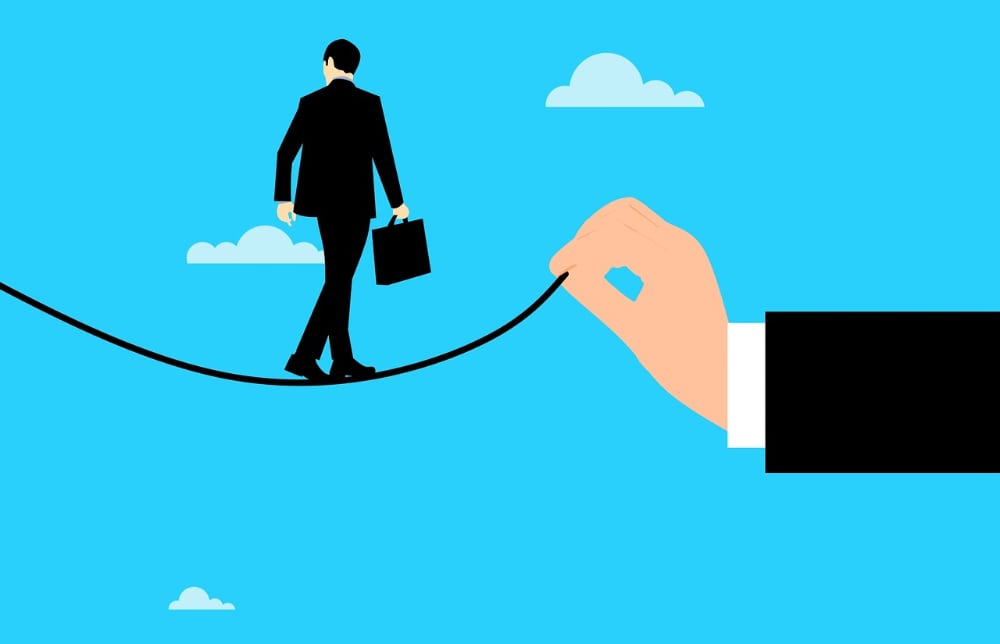
ゾンビ企業って2018年度では世界で約5,300社、これは10年前と比べて2倍超の水準だそうです。
これは、日本経済新聞が世界の上場企業26,000社の財務を調査した結果で、条件はこれ。
支払い利息が営業利益(本業のもうけ)を上回った企業。
ちょっと繰り返しますね。。
支払い利息が営業利益(本業のもうけ)を上回った企業。
支払い利息が営業利益(本業のもうけ)を上回った企業。
…そりゃあ『ゾンビ企業』と言われますよね。。
国際的な研究では、『ゾンビ企業』が増えた理由として、各国の中央銀行が進めてきた金融緩和による低金利環境の影響があるとの指摘も増えてきています。
個人に当てはめて考えてみてください。
超低金利下では、住宅ローンを組む心理的ハードルも低くなりますよね。個人の住宅ローンは利払いが収入で支払うことができない状態なんてありえませんが(笑)、金利が上がった際に支払いに無理が生じるような状態の場合、ゾンビ的な状態とも言えちゃうかもしれません。。
国際決済銀行(BIS)によると14の先進国で、名目金利が下がるほどゾンビ企業が増えるという相関関係ありと分析されています。
金融緩和の影響で、収益力や財務が弱い企業でも負債に頼って『ゾンビ』的に生きながらえてしまうわけですね。。
これって、とってもおそろしい。
自分の生存が金融緩和という外部によって左右されている場合、その命は永遠なのでしょうか。本来自然死しているはずのゾンビが今後さらに増殖した場合、そのいびつさは市場の混乱を招くことはないのでしょうか。
ですから個別株投資をする場合は、ゾンビ企業への投資は避けなければなりませんし、そもそもそんなリスクをキャンセルするものとして、投資信託やETFといった一括分散投資商品があるわけです。


ではこの『ゾンビ企業』。
見分けるにはどこに注目すればよいでしょうか。
ゾンビ企業への投資は避けたい!どこに注目すべき?

はじめにもう一度、日本経済新聞社の記事を引用しながら、『ゾンビ企業の数』について把握しておきましょう。
『ゾンビ企業』って言葉が少し強いですが、高成長に伴う積極投資の結果、数字上ゾンビに見える企業もあるため、言葉だけ独り歩きさせずに冷静に企業分析しましょうね。
日本、米国、欧州、中国、アジアの上場約2万6000社のうち、3年連続で支払利息が営業利益を上回った企業は、18年度に約5,300社と全体の20%を占めた。
地域別では欧州が1439社で最大。米国は923社、米企業に占める比率は32%。
業種別では医療。医薬品、非鉄、エネルギー、IT関連が目立つ。
例えば、米デル・テクノロジーズは、16年に米EMCを買収。その際に負債が膨らんで利払い額が急増し、営業利益を上回り続けている。
≪出所:日本経済新聞≫
ちなみに、日本企業は「カネ余り」で債務依存度が低く、ゾンビ企業は109社と少ないようです。
では、ゾンビ企業を回避して優良株へ投資するにはどのあたりに注意する必要があるでしょうか。
とはいえ、これまでみてきた『ゾンビ企業』の定義や特徴を見ていくと、それを避けるために抽象化しえる条件はこの2つと言えますよね。
- 財務状態が良いこと。つまりBSの状態
- 収益状態が良いこと。つまりPLとCFの状況
個人的には、
- 自己資本比率(負債比率)
- ROE
- 営業キャッシュフローマージン
には最低限注目しますし、これらの数字の過去5年~10年の推移を注視します。
ここではあえて、具体的な数値を挙げていません。
一個人投資家の見解に過ぎませんので、情報収集を重ねて自分なりのポイントを設けてみてくださいね。
日々の個別株チェックや実践についてはツイッターで発信しているので、ぜひフォローしてください。
また、株式投資に関する本質的なことが書いてある骨太な本や財務分析に関する入門書は、個別株投資を行うのであれば、目を通しておくべきですね。



それではまた~
ほぼ日刊、
投資関連コラムと運用実績のブログ。
更新情報はtwitterで!
応援のクリックをお願いします♬

 使いやすさNo.1楽天証券
使いやすさNo.1楽天証券| 使いやすさ | |
|---|---|
| コスト | |
| 情報量 |
 ドル転コスト№1SBI証券
ドル転コスト№1SBI証券| 使いやすさ | |
|---|---|
| コスト | |
| 情報量 |
 米国株の情報量が豊富!マネックス証券
米国株の情報量が豊富!マネックス証券| 使いやすさ | |
|---|---|
| コスト | |
| 情報の豊富さ |
ぼく自身は上記3社ともで口座を開設し、
メイン利用は楽天証券、
ETF積立はSBI証券、
情報収集はマネックス証券
と使い分けしています。